「杞憂」とは、「心配する必要のないことをあれこれ心配すること。取り越し苦労。」という意味があります。
しかし、杞憂の意味がわかったところで、その正しい使い方やシチュエーションを理解しておかないと、間違った解釈をしたまま恥ずかしい思いをするかもしれません。
そうならないように、この記事で杞憂の意味に加えて、正しい使い方を例文も交えてわかりやすく解説しておりますので、最後まで読んでこれから活用できるようにしてくださいね!
 ヒロト
ヒロト『杞憂』って言葉知ってる?
 コトハ
コトハええ。たしか“必要のない心配”って意味だったと思うけど。
「杞憂」の意味とは?わかりやすく解説
「杞憂」とは、きゆうと読み、心配する必要のないことをあれこれ心配すること。取り越し苦労。という意味があります。
杞憂の意味を辞書で調べると、このように解説されております。
【杞憂の意味】
goo辞書より引用
- 《中国古代の杞の人が天が崩れ落ちてきはしないかと心配したという、「列子」天瑞の故事から》
心配する必要のないことをあれこれ心配すること。取り越し苦労。
「杞憂」の意味
「杞憂(きゆう)」とは、「心配しなくてもいいことを、必要以上に気にしてしまうこと」を意味する言葉です。簡単に言うと、「取り越し苦労」や「考えすぎ」といった意味になります。実際には起こりそうもない悪いことを心配してしまうときに使われます。
「杞憂」の意味の概要
この言葉は、誰かがまだ起きてもいない問題について不安になっていたり、根拠のない心配をしていたりするときに使われます。たとえば、「明日のテスト、全然ダメかもしれない…」と落ち込んでいる友だちに対して、「そんなの杞憂だよ。ちゃんと勉強してたじゃん」と言って励ますことができます。
つまり「杞憂」は、心配する必要がないことを、まじめに悩んでしまっている様子を表す言葉です。
 ヒロト
ヒロト「杞憂」ってどんなことを意味するの?もう少し詳しく教えて!
 コトハ
コトハ杞憂(きゆう)とは、起こる可能性がほとんどないことを必要以上に心配することを表す言葉です。たとえば、まだ何も起きていないのに「失敗したらどうしよう」と不安になるようなときに使います。簡単に言えば「心配しすぎ」「取り越し苦労」という意味です。
「杞憂」の語源や由来
杞憂の語源や由来は以下のとおりです。
【杞憂の語源や由来】
weblio辞書より引用
- 「杞憂」は中国の古典文献「列子」の記述に由来する故事成語である。
- 古代、杞の国に住む男が、「この天地が崩落するようなことがあったらどうしよう」という不安に駆られ、心配のあまり寝食もままならず憔悴していた。周りの者は、そんなことは起こらないと言い聞かせて男を安堵させたという。
- この「杞人の憂い」の話が、「心配する必要のないことを心配する」こと、または「心配してもしょうがない(心配したとてどうこうできるものではない)ことを心配する」こと、要するに「無駄に心配すること」「取り越し苦労」を端的に示す話として今日に伝わっているわけである。
「杞憂」の語源や由来
杞憂(きゆう)という言葉は、中国の昔話から生まれたものです。ここでいう「杞(き)」は、昔の中国にあった小さな国の名前です。
この国に住んでいたある男性が、ある日「空が落ちてきたらどうしよう」「地面がなくなったらどうなるんだろう」と本気で心配して、毎日眠れなくなってしまったそうです。まわりの人が「そんなこと起きるはずがないよ」と言っても、本人は不安でたまらなかったといいます。
このエピソードがもとになって、「ありえないことを心配しすぎること」を「杞憂」と呼ぶようになりました。つまり、「杞の国の人の心配ごと(=杞憂)」という意味です。
今では、何かを心配しすぎている人に「それは杞憂だよ」と言えば、「そんなに心配しなくて大丈夫だよ」という優しい声かけとして使える言葉になっています。
「杞憂」の使い方を例文でわかりやすく解説
それでは、「杞憂」の正しい使い方を具体的にイメージできるようわかりやすい例文をご紹介します。
 ヒロト
ヒロト杞憂ってどういう場面で使ったりするの?
 コトハ
コトハ「杞憂」は、まだ起きていないことを心配しすぎている場面で使われます。たとえば、失敗を必要以上に恐れたり、ありえない最悪のケースを想像して不安になっているときに使います。
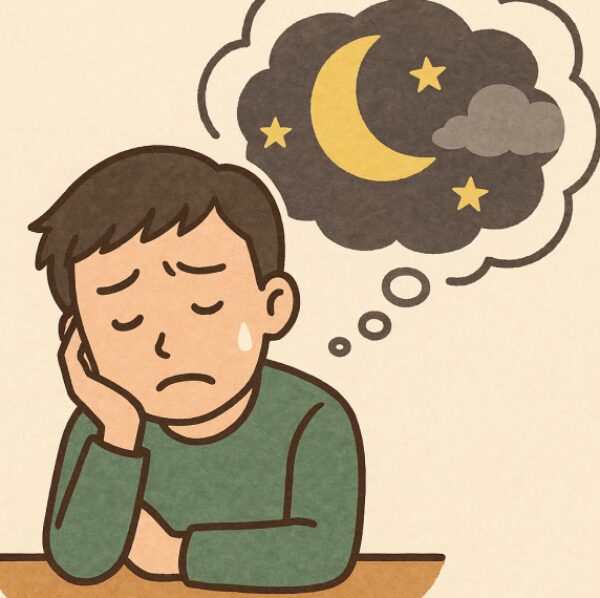
- 心配していたことが起こらなかったとき。
- 自分の不安がただの思い過ごしだったとき。
- 他人の不安が大げさだとやんわり指摘するとき。
- プレゼンや報告で「心配しすぎかもしれませんが…」と前置きしたいとき。
- 試験や面接の結果が意外と良かったとき。
- 相手の心配を軽く見ているように受け取られないよう、使い方に配慮する。
- 「杞憂」は悪い意味だけでなく、安心した気持ちを表すときにも使えることを意識する。
- 場合によっては、もっとやわらかい言葉(例:取り越し苦労)に置きかえたほうが無難。
杞憂の例文①
友達が「今日の部活でミスしたらどうしよう…」と朝から不安がっていたけれど、実際はうまくいったケース。
 ヒロト
ヒロト部活での発表、大成功だったね。
 コトハ
コトハ「ミスしたらどうしよう…」と不安だったけど、杞憂だったわ。
 ヒカル
ヒカルこの例では、「思っていたよりもうまくいった」結果を受けて、過剰な心配が必要なかったと伝えています。
杞憂の例文②
会議で新しい企画を提案する前に、「もしかしたら誰も賛成してくれないかも…」と不安に思っている場面。
 ヒロト
ヒロト会議で新しい企画を提案するんだって?準備は大丈夫?
 コトハ
コトハええ。杞憂かもしれないけど、この案に反対意見が出たときの対応も考えておくわ。
 ヒカル
ヒカルこの使い方は、ビジネスや学校の発表などでよく見られます。「心配しすぎかもしれないけど、念のため…」というニュアンスで、慎重な姿勢をアピールできます。
杞憂の例文③
模試の結果が悪かったと思い込んだ友人が「もう本番もダメかも…」と落ち込んでいたが、実際は本番で高得点を取ったケース。
 ヒロト
ヒロト模試の結果が悪かったから、本番も絶対にダメだと思ったけど、どうにかなったよ!
 コトハ
コトハ本番であんなに点が取れたんだから、あの落ち込みは杞憂だったね。
 ヒカル
ヒカルこの場合は、過去の過剰な不安を振り返って「必要なかったね」とやさしく指摘する使い方です。励ましのニュアンスが強く、日常会話でよく使える表現です。
「杞憂」の言い換え表現を例文を使ってわかりやすく解説
「杞憂」には以下のような言い換え表現があります。
【杞憂の言い換え表現】
- 取り越し苦労(とりこしくろう):まだ起きてもいないことをあれこれ心配して、必要以上に苦しむこと。
- 思い過ごし(おもいすごし):実際にはそうではないのに、自分の中で勝手に悪い方向に考えてしまうこと。
「取り越し苦労」の例文
取り越し苦労(とりこしくろう)とは、まだ起きてもいないことをあれこれ心配して、必要以上に苦しむことです。結果的に何も問題が起こらなければ、その心配はムダだったということになります。「杞憂」とほぼ同じ意味ですが、日常会話での登場頻度は高く、柔らかい印象があります。
「面接で変なことを言っちゃったかも」と一晩中悩んでいたが、翌日合格通知が来た場面です。
 ヒロト
ヒロト面接で変なこと言っちゃったから絶対ダメだと思ってたのに合格したよ!
 コトハ
コトハ合格おめでとう!、あの心配は取り越し苦労だったねわ。
 ヒカル
ヒカル「杞憂」に比べて、取り越し苦労はややくだけた表現で、相手との距離が近いときに使いやすいです。友達同士や家族との会話に向いています。
「思い過ごし」の例文
「思い過ごし」は、実際にはそうではないのに、自分の中で勝手に悪い方向に考えてしまうことです。過剰な不安だけでなく、勘違いによる心配にも使えます。「杞憂」よりもくだけた口調で、カジュアルな会話向きです。
「昨日のLINEの返信、そっけなかったけど怒ってるのかな?」と心配していたが、実際は相手がただ忙しかっただけだったことがわかった場面。
 ヒロト
ヒロトコトハ、昨日のLINEの返事、そっけなかったけど、何か怒ってる?
 コトハ
コトハえー!!それは思い過ごしよ。昨日は忙しくて短く返しただけだって。
 ヒカル
ヒカル「思い過ごし」は、「取り越し苦労」や「杞憂」よりも軽い印象で、ちょっとした誤解や気のせいにも使えます。深刻な状況よりも、日常の小さな心配事に向いています。
「杞憂」の類義語
「杞憂」とまったく同じ意味の言葉はありませんが、似た意味を持つ言葉として「懸念(けねん)」と「危惧(きぐ)」があります。どちらも、まだ起きていないことを心配する気持ちを表すときに使いますが、少しずつニュアンスが異なります。
【杞憂と似た意味をもつ言葉】
- 懸念(けねん):これから起こるかもしれないことを心配して、気になる気持ちを表します。
- 危惧(きぐ):これが悪い結果につながるのではと心配し、恐れる気持ちを表します。
「懸念(けねん)」の例文
「懸念」は、これから起こるかもしれない出来事や結果について、不安や心配を抱くことです。心配の強さは比較的おだやかで、日常会話からビジネス文書まで幅広く使えます。
 ヒロト
ヒロトここのところ雨が続いているけど、運動会大丈夫かな?
 コトハ
コトハそうね。このまま雨が降り続くと、運動会の開催が懸念されるわね。
 ヒカル
ヒカルこの例では、「雨のせいで運動会ができなくなるかもしれない」という不安をやわらかく表現しています。「杞憂」は心配が不要だったときに使うことが多いですが、「懸念」はその心配がまだ続いている状況にも使えるのが違いです。
「危惧(きぐ)」の例文
「危惧」は、物事が悪い方向に進むのではないかと強く心配し、恐れることを表します。「懸念」よりも不安の度合いが大きく、深刻な場面で使われやすい言葉です。
 ヒロト
ヒロト例の計画、順調に進んでいるの?
 コトハ
コトハいいえ。この計画は予算が足りないため、実行が難しくなることを危惧しています。
 ヒカル
ヒカルこの例では、「計画がうまく進まないかもしれない」という強い不安を表しています。「危惧」はビジネスや報道などの文章でよく使われ、日常会話ではやや硬い印象です。日常的に使うなら、「心配している」や「不安に思う」に置きかえても良いでしょう。
「杞憂」の対義語
「杞憂」に明確な対義語はありませんが、反対の意味を持つ言葉として、ここでは「安心(あんしん)」と「楽観(らっかん)」を紹介します。
どちらも「心配しない」「不安がない」という点で共通していますが、ニュアンスや使い方は少し異なります。
【杞憂と反対の意味をもつ言葉】
- 安心(あんしん):心配や不安がなく、気持ちが落ち着いていること。
- 楽観(らっかん):物事が良い方向に進むと考え、あまり心配しないこと。
「安心(あんしん)」の例文
「安心」は、心配や不安がなく、気持ちが落ち着いていることを意味します。
試験の合格通知を受け取ったときや、病気の検査結果に問題がなかったときなどの場面で使われます。
 ヒロト
ヒロト台風直撃の予報が出ていたけど、大丈夫だったね!
 コトハ
コトハそうね!台風が進路を変えてくれて安心したわ。
 ヒカル
ヒカル不安がなくなってホッとした気持ちを表します。「杞憂」とセットで使うと、「あの心配は杞憂だったから安心した」というように、対比が分かりやすくなります。
「楽観(らっかん)」の例文
「楽観」とは、物事が良い方向に進むと考え、あまり心配しないことを意味します。
結果が分からないときでも「きっと大丈夫」と思える人の考え方や態度を表します。
 ヒロト
ヒロトBくん試験前でも早く寝ちゃうんだって。
 コトハ
コトハ彼はいつも楽観的で、試験の前日でも早く寝てしまうそうよ。
 ヒカル
ヒカル「楽観」は、根拠があってもなくても「大丈夫だろう」と前向きに考える態度です。「杞憂」とは正反対で、不安よりも期待の気持ちが強い場面で使います。
「杞憂」の英語表現
「杞憂」にぴったり同じ英語はありませんが、似た意味を持つ表現としてここでは、 unfounded fear(根拠のない恐れ)と、 needless worry(必要のない心配)を挙げます。どちらも「実際には起こらないことを心配する」というニュアンスを持っています。
【杞憂の英語】
- unfounded fear:根拠のない恐れ。理由のない心配。“unfounded” は「根拠のない」という形容詞で、“fear” は「恐れ」を意味。
- needless worry:必要のない心配。ムダな心配。“needless” は「必要ない」という形容詞で、“worry” は「心配」という意味。
「unfounded fear」の例文
「unfounded fear」は、「根拠のない恐れ」「理由のない心配」という意味です。“unfounded” は「根拠のない」という形容詞で、“fear” は「恐れ」を意味します。
 ヒロト
ヒロト「杞憂」の英語表現「unfounded fear」を使った例文を教えて!
 コトハ
コトハ"It turned out that my fear of failing the exam was an unfounded fear."のように表現することができます。
日本語訳:試験に落ちるかもしれないという私の心配は、杞憂に終わった。
 ヒカル
ヒカルこの表現は、心配の原因に根拠がないことを強調するときに使います。少しフォーマルな響きがあるので、レポートやスピーチなどでも使いやすいです。
「needless worry」の例文
「needless worry」は、「必要のない心配」「ムダな心配」という意味です。“needless” は「必要ない」という形容詞で、“worry” は「心配」という意味です。
 ヒロト
ヒロト「杞憂」の英語表現「needless worry」を使った例文を教えて!
 コトハ
コトハ”Her concern about the weather ruining the picnic was just needless worry.”のように表現することができます。
日本語訳:天気がピクニックを台無しにするという彼女の心配は、ただの杞憂だった。
 ヒカル
ヒカル「needless worry」は、日常会話でとても使いやすい表現です。特に、友達や家族との会話で「そんなに心配する必要ないよ」というニュアンスをやわらかく伝えるときに向いています。
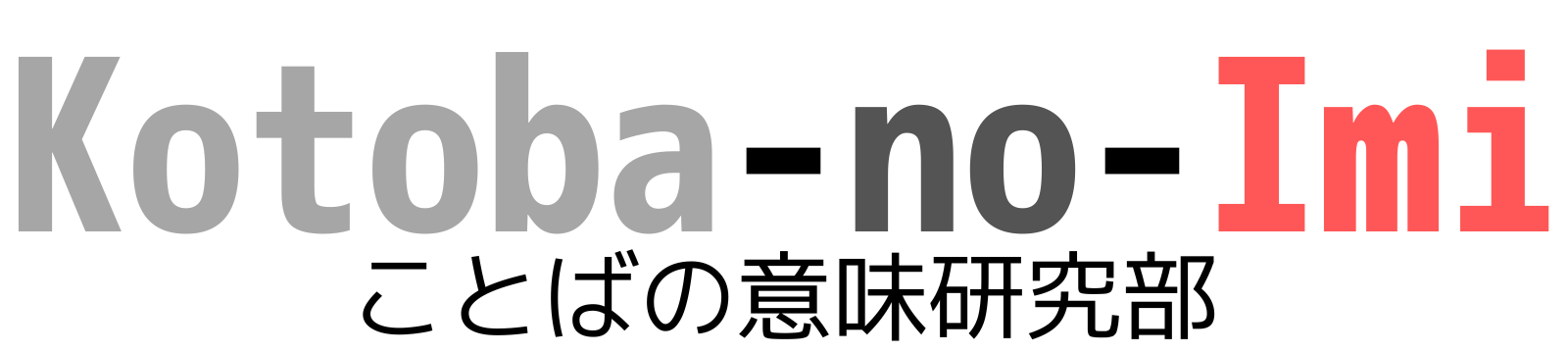
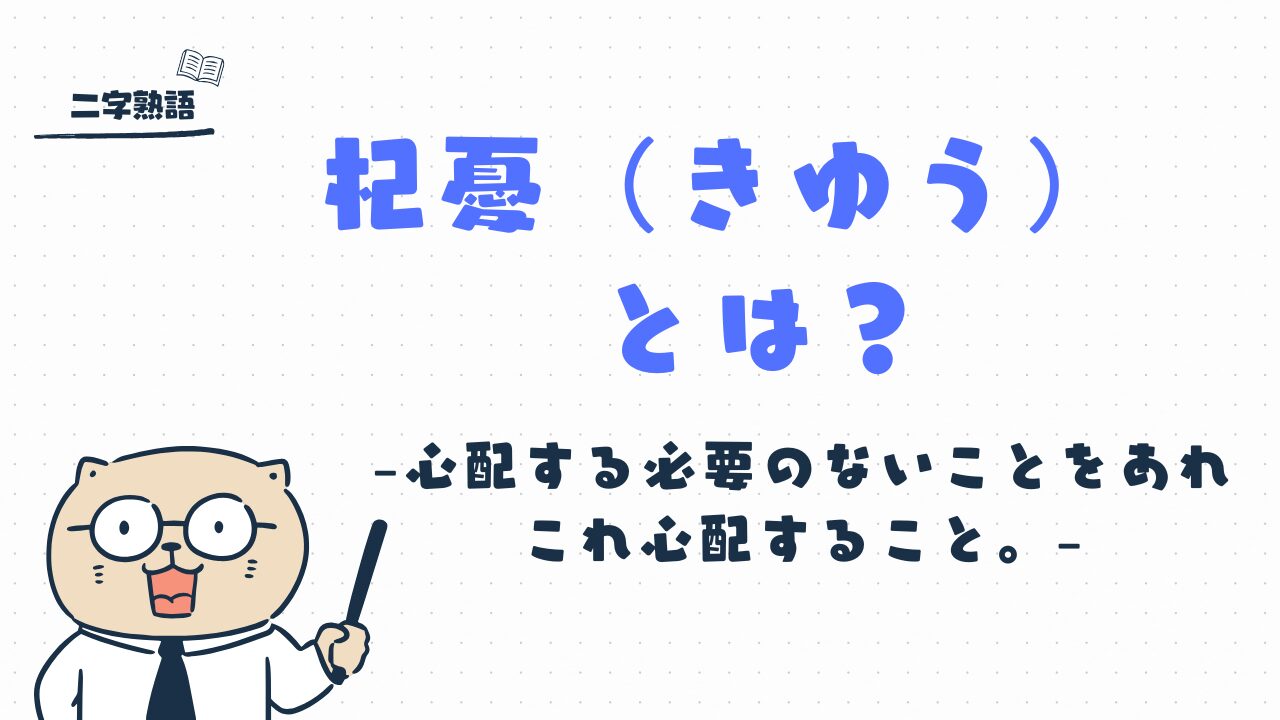
コメント