「岡目八目」とは、「当事者よりも、傍観者のほうが物事の情勢を正確に判断できることのたとえ。」という意味があります。
しかし、岡目八目の意味がわかったところで、その正しい使い方やシチュエーションを理解しておかないと、間違った解釈をしたまま恥ずかしい思いをするかもしれません。
そうならないように、この記事で岡目八目の意味に加えて、正しい使い方を例文も交えてわかりやすく解説しておりますので、最後まで読んでこれから活用できるようにしてくださいね!
 ヒロト
ヒロト岡目八目って、当事者よりも周りの人の方がよく見えるって意味だよね。
 コトハ
コトハそうそう、だから人の相談には冷静にアドバイスできるのよね。
「岡目八目」の意味とは?わかりやすく解説
「岡目八目」とは、「おかめはちもく」と読み、当事者よりも、傍観者のほうが物事の情勢を正確に判断できることのたとえ。という意味があります。
岡目八目の意味を辞書で調べると、このように解説されております。
【岡目八目の意味】
四字熟語辞典より引用
- 当事者よりも、傍観者のほうが物事の情勢を正確に判断できることのたとえ。
「岡目」は、他人の行動を横から見ること。
囲碁では、対局者よりも観戦者のほうが冷静に局面を見通し、八手先まで予測できるといわれることに由来する言葉。
岡目八目の意味
岡目八目(おかめはちもく)とは、当事者よりも第三者の方が、物事の状況を正しく判断できる という意味の四字熟語です。囲碁の世界から生まれたことばで、自分が夢中になっていると視野が狭くなりがちですが、外から冷静に見ている人の方が全体像をよく理解できる、というたとえに使われます。
岡目八目の意味の概要
この四字熟語は、日常生活やビジネスシーンでもよく使われます。たとえば、自分のこととなると冷静さを失ってしまう人も、友人の悩み事なら客観的に良いアドバイスができる場合があります。つまり「人のことはよく見えるが、自分のことは見えにくい」という人間の特徴を表しているのです。そのため、恋愛・進路・仕事の判断など、幅広い場面で例えとして登場します。
岡目八目をわかりやすく解説
身近な例でいうと、部活の試合中にプレーしている本人は熱くなってミスをしてしまうことがありますが、観客や監督は冷静に試合の流れを把握しています。これがまさに「岡目八目」です。つまり、物事は客観的に見た方が冷静で正しい判断につながる という教えを、この四字熟語はわかりやすく表現しています。
 ヒロト
ヒロト「岡目八目」ってどんなことを意味するの?もう少し詳しく教えて!
 コトハ
コトハ「岡目八目」とは、当事者よりも周りで見ている人の方が、状況を冷静に判断できるという意味です。囲碁の世界から生まれた言葉で、打っている本人よりも、横で見ている人の方が数手先の展開がよく見えることをたとえています。日常では「人のことはよく見えるが、自分のことは見えにくい」という意味で使われます。
「岡目八目」の語源や由来
岡目八目の語源や由来は以下のとおりです。
【岡目八目の語源や由来】
Domaniより引用
- 「岡目八目」は、囲碁に由来する言葉です。「岡目八目」の「岡目」は「わきから見ること」を指しており、「八目」は「碁盤の目や手数のこと」を指しています。
- 囲碁の世界では自分が対局しているときは、つい主観的になり、打ち間違えたり悪い手を打ってしまったりすることがあります。そんな時には、わきから見ている観客のほうが冷静に勝負の行方を判断できるものです。その状況をたとえた言葉として「岡目八目」が使われるようになりました。
「岡目八目」の語源や由来
「岡目八目」という四字熟語は、囲碁(いご) に由来しています。囲碁では、黒と白の石を交互に打って陣地を広げますが、実際に対局している人は、自分の手に集中しすぎて全体を見失ってしまうことがあります。
ところが、横で観戦している人は気持ちが冷静な分、試合の流れを客観的に見ることができます。そのため、プレイヤーが気づかない「あと数手で勝敗が決まる展開」にも気づけるのです。この「八目」というのは、「八手先」や「八つの石の差」といった意味合いで、「外から見ている人の方が八目先まで見通せる」というたとえ から生まれました。
つまり「岡目八目」は、囲碁を観戦している立場の人が、実際に打っている人よりも先の展開をよく理解できることを示す表現であり、そこから「当事者より第三者の方が冷静で正しい判断ができる」という意味に発展したのです。
「岡目八目」の使い方を例文でわかりやすく解説
それでは、「岡目八目」の正しい使い方を具体的にイメージできるようわかりやすい例文をご紹介します。
 ヒロト
ヒロト「岡目八目」ってどういう場面で使ったりするの?
 コトハ
コトハ「岡目八目」は、当事者よりも第三者の方が状況を冷静に判断できる、という意味のことわざです。たとえば将棋や囲碁の対局を横から見ている人が、当事者よりも次の一手を正しく見抜けるような場面で使われます。日常生活でも、友達の恋愛やトラブルを傍から見ていると、当事者が気づかない問題点や解決策がよく見える、という場面でよく使われます。

「岡目八目」は、次のような場面でよく使われます。
- 恋愛相談で、本人よりも周囲の友人が冷静にアドバイスするとき
- 勉強や受験で、本人よりも先生や保護者の方が全体を見ているとき
- スポーツの試合で、プレーヤー本人より監督や観客の方が流れを理解できるとき
- ビジネスの会議で、当事者同士よりも第三者の意見が正確なとき
- 家族や友人のトラブルで、当人同士より外から見る人の方が状況をよく理解できるとき
- 人の悩みや失敗に対して「岡目八目だね」と言うと、上から目線に聞こえる場合がある
- 自分のことに使うのではなく、基本的には「他人の様子を外から見る」場面で使う
- くだけた日常会話では伝わりにくいことがあるので、適度に説明を加えると親切<注意点1>
岡目八目の例文①
恋愛相談の場面で、本人は冷静に判断できていないけれど、友人は状況をよく見えているケースです。
 ヒロト
ヒロト友達が恋愛相談してきたんだけど、相手の気持ちがよく見えるんだよね。
 コトハ
コトハそれは岡目八目ね。当事者よりも、そばで見てる人の方が冷静に判断できるのよ。
 ヒカル
ヒカルそうね。恋している本人は感情に流されがちだけど、外から見ている友達は状況を客観的に判断できるの。これがまさに岡目八目ってことなのよ。
この例文では、恋愛という感情が大きく動く場面で、第三者の視点の方が冷静に物事を見通せることを表しています。
岡目八目の例文②
サッカーの試合で、プレーヤー本人よりも監督や観客が試合の流れをよく見えているケースです。
 ヒロト
ヒロトサッカーの試合って、見てると『そこにパス出せばいいのに!』って思うんだよね。
 コトハ
コトハそれも岡目八目ね。プレーしている本人よりも、観戦している人の方が落ち着いて全体を見られるのよ。
 ヒカル
ヒカルええ。選手は緊張や焦りで視野が狭くなってしまうの。でも観客や監督は冷静に試合を見ているから、先の展開まで見通せるのよ。
スポーツでは特に、当事者よりも観客の方が「次の一手」がよく見えることがあります。これも岡目八目の典型的な使い方です。
岡目八目の例文③
会議で、直接かかわっていない第三者の方が問題点に気づきやすいケースです。
 ヒロト
ヒロト会議で別の部署の人が意見をくれたんだけど、核心を突いててびっくりしたよ。
 コトハ
コトハそれってまさに岡目八目ね。関係者よりも、外から見ている人の方が正しい判断をすることがあるのよ。
 ヒカル
ヒカルそうね。会議に深くかかわる人は細かい部分に気を取られやすいの。でも、第三者は全体を客観的に見られるから、本質に気づけるのよ。
ビジネスの現場でも「岡目八目」は使われます。関係者が見落としている点を、外部の人が冷静に指摘できるのです。
「岡目八目」の言い換え表現を例文を使ってわかりやすく解説
「岡目八目」は少しむずかしい四字熟語なので、普段の会話ではもっと簡単な言い方に置きかえることもできます。ここでは代表的な2つを紹介します。
【岡目八目の言い換え表現】
・言い換え表現①:「第三者の方がよく見える」
・言い換え表現②:「人のことはよくわかる」
「第三者の方がよく見える」の例文
友達の進路相談で、本人は悩んでいるけれど、外から見ている人の方が冷静に考えられるケース。
 ヒロト
ヒロト進路って本人は迷うけど、周りの人の方が答えを出しやすい気がするな。
 コトハ
コトハそうね、第三者の方がよく見えるってことよ。当事者よりも冷静に考えられるものなの。
 ヒカル
ヒカルここで『岡目八目』と言い換えても意味は同じね。でも『第三者の方がよく見える』の方がやさしくて、日常会話で自然に使える表現なのよ。
「岡目八目」よりもくだけた言い方で、中高生や日常会話にぴったり。専門的な雰囲気を出したいときは「岡目八目」、やわらかく伝えたいときは「第三者の方がよく見える」が向いています。
「人のことはよくわかる」の例文
恋愛相談で、本人は相手の気持ちがわからないけれど、友達にはよく見えているケース
 ヒロト
ヒロト友達が恋愛相談してきたんだけど、僕から見ると相手の気持ちがよく分かるんだよね。
 コトハ
コトハやっぱり人のことはよくわかるのよね。本人よりも、そばで見ている人の方が冷静だから。
 ヒカル
ヒカルここで『岡目八目』と表現すれば四字熟語らしくなるけど、『人のことはよくわかる』の方が親しみやすいわ。場面に応じて使い分けられると便利よ。
「人のことはよくわかる」はとても日常的で、家族や友人との会話で自然に使えます。比喩として少し格調を出したいときは「岡目八目」を選ぶとよいでしょう。
「岡目八目」の類義語
「岡目八目」には、似たような意味をもつ言葉がいくつかあります。ここでは、以下の2つを紹介します。
【岡目八目の類義語】
Domaniより引用
- 他人の正目(たにんのまさめ):他人の判断が正しい
- 灯台下暗し(とうだいもとくらし):事者だから気づかない
「他人の正目」の例文
他人の正目(たにんのまさめ)とは、他人の欠点や短所はよく見えるが、自分のことは気づきにくい という意味のことばです。
「岡目八目」と同じように「人のことはよく見えるが、自分のことは見えにくい」という特徴を表しています。
 ヒロト
ヒロト友達の性格の短所ってすぐ気づくのに、自分のことはなかなかわからないんだよな。
 コトハ
コトハそれは『他人の正目』っていうのよ。他人のことはよく見えるけど、自分のことは気づきにくいものなの。
 ヒカル
ヒカルそうね。岡目八目が『判断の正確さ』を強調しているのに対して、他人の正目は『自分の欠点には気づきにくい』という点を表すの。場面によって使い分けできるわね。
「他人の正目」は、主に人間関係や性格の話題で使われることが多い表現です。岡目八目が「状況を客観的に判断する」というニュアンスが強いのに対し、「他人の正目」は「自分のことには鈍感」という側面に焦点を当てています。
「灯台下暗し」の例文
灯台下暗し(とうだいもとくらし)とは、灯台は遠くを明るく照らすけれど、すぐ足元は意外と暗い ということから、身近すぎるものはかえって気づきにくい という意味を表すことわざです。
岡目八目と同じく「自分には見えにくいが、他人からは見えやすい」という共通点があります。
 ヒロト
ヒロト家のすぐ近くにあるお店、最近まで気づかなかったんだよ。
 コトハ
コトハそれは『灯台下暗し』ね。身近なことって案外見落としやすいのよ。
 ヒカル
ヒカルそうそう。岡目八目が『他人の方が正しく判断できる』という意味なのに対して、灯台下暗しは『近すぎて見えない』ことを表すの。似ているけど、使う場面は少し違うのよ。
「灯台下暗し」は、日常生活での「身近なことに気づかない」エピソードでよく使われます。岡目八目のように「第三者の冷静さ」を示すのではなく、「自分の身近なことを見落としてしまう」という教訓を含む表現です。
「岡目八目」の対義語
「岡目八目」にはっきりした対義語はありませんが、反対の意味をもつ言葉や、逆の立場を表すことわざは存在します。ここではその中から代表的なものを2つ紹介します。
【岡目八目の対義語】
・あばたもえくぼ
・鹿を逐う者は山を見ず
「あばたもえくぼ」の例文
「あばたもえくぼ」とは、恋をしていると、相手の欠点さえ魅力的に見えてしまう という意味のことわざです。
「岡目八目」が冷静で客観的な判断を表すのに対し、こちらは「当事者は冷静さを失い、正しく見られなくなる」という逆の考えを示しています。
 ヒロト
ヒロト友達が恋人のことをすごくほめてたんだけど、正直ちょっと変わった人なんだよね。
 コトハ
コトハそれは『あばたもえくぼ』ね。好きになると欠点すら良く見えちゃうのよ。
 ヒカル
ヒカルそうね。岡目八目は“第三者が冷静に判断できる”という意味だけど、あばたもえくぼは“当事者が冷静さを失う”という真逆の状態を表すのよ。
このことわざは、主に恋愛の場面でよく使われます。第三者は欠点に気づけるのに、当事者にはそれが見えない――岡目八目の逆の立場を表すことばです。
「鹿を逐う者は山を見ず」の例文
「鹿を逐う(おう)者は山を見ず」とは、夢中になりすぎると周りが見えなくなる という意味のことわざです。
「岡目八目」が「冷静に全体を見通せる」ことを強調するのに対し、こちらは「当事者は一つのことにとらわれて視野が狭くなる」という逆の意味を表します。
 ヒロト
ヒロト試験勉強で一つの問題にこだわりすぎて、気づいたら時間切れになったよ。
 コトハ
コトハそれは『鹿を逐う者は山を見ず』っていうのよ。目の前のことに夢中になって、全体が見えなくなるの。
 ヒカル
ヒカルその通りね。岡目八目が“外から見れば冷静に全体を把握できる”ことを表すのに対して、鹿を逐う者は山を見ずは“当事者は視野が狭くなる”という対照的な意味を持つのよ。
このことわざは、勉強や仕事など集中しすぎて全体を見失うときに使われます。客観的に見られる岡目八目と違い、夢中になった当事者が視野を失う状態を表しています。
岡目八目:第三者の方が冷静に物事を判断できる
あばたもえくぼ:当事者は冷静さを失い、欠点すら良く見える
鹿を逐う者は山を見ず:夢中になりすぎて周囲が見えなくなる
「岡目八目」の英語表現
「岡目八目」には同じ意味の英語のことばはありませんが、近い意味を表せる表現があります。ここでは代表的な2つを紹介します。
【岡目八目の英語】
・英語表現①:An onlooker sees most of the game
・英語表現②:It’s easier to see things from the outside
「An onlooker sees most of the game」の例文
「An onlooker sees most of the game」は、直訳すると「見物人は試合の大半が見える」ということわざです。
つまり、当事者よりも外から見ている人の方が全体を冷静に見渡せる、という意味で「岡目八目」と非常に近いニュアンスを持っています。
 ヒロト
ヒロト「岡目八目」を英語で表現した例文を教えて!
 コトハ
コトハ"Don’t worry too much. Remember, an onlooker sees most of the game."のように表現することができます。
日本語訳:そんなに悩みすぎないで。ほら、見ている人の方が全体をよく見えるものだよ。
 ヒカル
ヒカルこの表現は、友人にアドバイスをするときなどに自然に使えます。「岡目八目」の意味をそのまま英語で伝えたいときに便利です。
「It’s easier to see things from the outside」の例文
「It’s easier to see things from the outside」は、直訳すると「外からの方が物事は見やすい」という意味です。
シンプルでわかりやすく、日常会話にとても使いやすい表現です。
 ヒロト
ヒロト「岡目八目」を英語で表現した例文をもう1つ教えて!
 コトハ
コトハ"Sometimes it’s easier to see things from the outside than when you are in the middle of the problem."のように表現することができます。
日本語訳:ときには、問題の真ん中にいるよりも、外からの方がよく見えることがあるんだ。
 ヒカル
ヒカルこの表現は、恋愛相談や仕事の相談など幅広い場面で使えます。カジュアルな言い回しなので、中高生でも自然に理解できます。
- An onlooker sees most of the game → ことわざ風の表現。格言っぽく使える。
- It’s easier to see things from the outside → 日常的でシンプル。普段の会話に使いやすい。
まとめ
「岡目八目(おかめはちもく)」は、当事者よりも第三者の方が冷静に物事を判断できる という意味を持つ四字熟語です。
囲碁の世界から生まれ、恋愛・勉強・スポーツ・仕事など、私たちの日常のあらゆる場面で使える表現です。
- 語源:囲碁の観戦者の方が八目先まで見通せることから
- 使い方:本人は冷静さを欠くが、周囲は全体を把握できる場面
- 類義語:「他人の正目」「灯台下暗し」など
- 対義語的表現:「あばたもえくぼ」「鹿を逐う者は山を見ず」など
- 英語表現:「An onlooker sees most of the game」「It’s easier to see things from the outside」
👉 この四字熟語を知っておくと、物事を客観的に見る大切さを日常でも意識できるようになります。
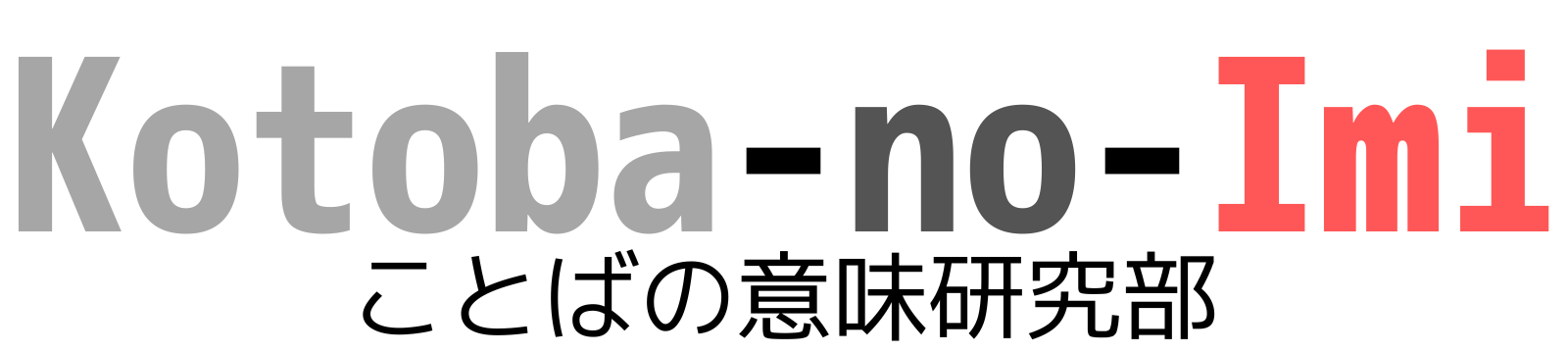

コメント