「甲論乙駁」とは、「議論の結論が出ないこと。」という意味があります。
しかし、甲論乙駁の意味がわかったところで、その正しい使い方やシチュエーションを理解しておかないと、間違った解釈をしたまま恥ずかしい思いをするかもしれません。
そうならないように、この記事で甲論乙駁の意味に加えて、正しい使い方を例文も交えてわかりやすく解説しておりますので、最後まで読んでこれから活用できるようにしてくださいね!
 ヒロト
ヒロト甲論乙駁って、結局どんな意味なの?
 コトハ
コトハみんなが言いたい放題で、意見がまとまらない状態のことよ!
「甲論乙駁」の意味とは?わかりやすく解説
「甲論乙駁」とは、こうろんおつばくと読み、議論の結論が出ないこと。という意味があります。
甲論乙駁の意味を辞書で調べると、このように解説されております。
【甲論乙駁の意味】
四字熟語辞典より引用
- 議論の結論が出ないこと。
「論」は意見を出すこと。
「駁」は反対の意見を出すこと。
「甲」が意見を出すと「乙」が反対の意見を出すということから、互いに意見を出したり反論したりするだけで、いつまでも結論が出ないという意味。
甲論乙駁の意味
甲論乙駁(こうろんおつばく)とは、ある人が意見を出すと、すぐに別の人が反対意見を言い返し、議論がなかなかまとまらないことを表す四字熟語です。
「甲」は一方の意見、「乙」はもう一方の意見を指し、それぞれが論じ合って相手を駁(ばく:論破・反論)する様子を表しています。つまり、意見が対立して平行線をたどる状態を示すことばです。
甲論乙駁の意味の概要
この表現は、単に「口げんか」というよりも、もっと真剣に意見を戦わせる場面で使われます。
たとえば政治の議論、学者どうしの討論、あるいはクラスでのディベートなど、さまざまな立場の意見がぶつかって決着がつかない様子を表すのにぴったりです。
「議論が絶えない」「互いに主張をぶつけ合っている」と言い換えることもできます。
甲論乙駁をわかりやすく解説
簡単にいうと「人が集まって話し合うと、いろんな意見が出ておさまらないこと」を表す言葉です。誰かが「こうすべきだ」と言えば、別の人が「いや、それは違う」と反論する。さらに別の人が新しい意見を出して、ますます収拾がつかなくなる。そんなイメージを四字熟語にしたのが「甲論乙駁」です。学校生活やニュースなど、身近な場面でもよく見かける状況を表現できる便利な言葉です。
 ヒロト
ヒロト「甲論乙駁」ってどんなことを意味するの?もう少し詳しく教えて!
 コトハ
コトハ一方が意見を出すと、すぐに別の人が反論し、議論がまとまらなくなることを表す四字熟語よ。「甲」は一方の意見、「乙」はもう一方の意見を指し、お互いに主張をぶつけ合っているイメージです。ディベートや討論番組のように、意見が入り乱れて収拾がつかない場面で使われます。
「甲論乙駁」の語源や由来
甲論乙駁の語源や由来は以下のとおりです。
【甲論乙駁の語源や由来】
四字熟語の百科事典より引用
- 「甲論乙駁」の語源・由来は、「甲」の人が論じると、それに対して「乙」の人が反対する、つまり互いに意見を述べ合い、反論し合うことを表しています。
このことから、議論がエスカレートして収拾がつかない状況を指すようになった四字熟語です。
甲論乙駁(こうろんおつばく)という言葉は、中国の古い書物に出てくる表現がもとになっています。
「甲(こう)」は一方の意見、「乙(おつ)」はもう一方の意見を表しています。つまり、ある人が「甲の立場」で意見を言えば、すぐに別の人が「乙の立場」で反論する、というやりとりの様子をそのまま言葉にしたのです。
この表現は、昔の学者や役人たちが集まって議論をするときに使われることが多かったといわれています。互いに「自分が正しい」と主張し合い、話がなかなかまとまらない姿を、「甲が論じて乙が駁(ばく=反論)する」と表現したのです。
つまり「甲論乙駁」という四字熟語は、議論が白熱して、あちこちから意見や反論が出て収拾がつかない様子を生き生きと伝えているのです。
「甲論乙駁」の使い方を例文でわかりやすく解説
それでは、「甲論乙駁」の正しい使い方を具体的にイメージできるようわかりやすい例文をご紹介します。
 ヒロト
ヒロト甲論乙駁ってどういう場面で使ったりするの?
 コトハ
コトハ甲論乙駁(こうろんおつばく)とは、一方が意見を出せば、もう一方が反論し、議論がなかなかまとまらないことを意味します。「甲」は一方の意見、「乙」はもう一方の意見を表し、互いに主張をぶつけ合っているイメージです。学校のディベートやニュースの討論番組など、意見が入り乱れて収拾がつかない場面を表すのにぴったりな四字熟語です。
※ディベート:特定のテーマ(論題)に対して、参加者が賛成(肯定)側と反対(否定)側の二つの立場に分かれ、ルールに基づいて論理的に討論を行う手法。
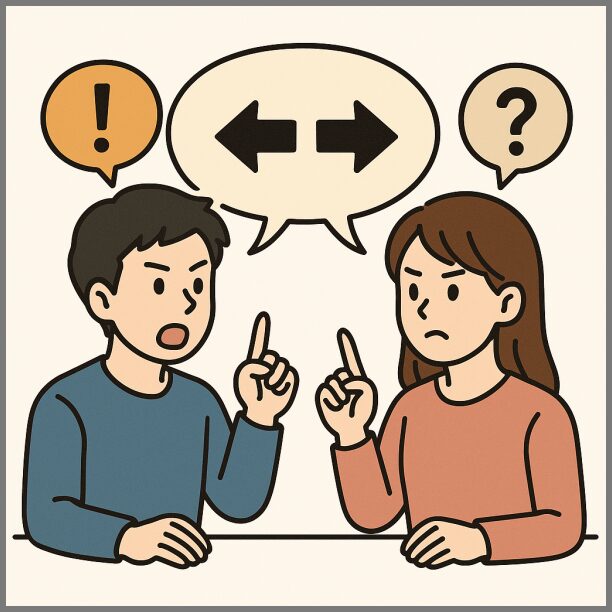
「甲論乙駁」は次のような場面でよく使われます。
- 学校の討論会やディベートで意見がまとまらないとき
- 政治家や専門家がテレビで議論しているとき
- クラスで進路や文化祭の企画を話し合っているとき
- 友達どうしが意見をぶつけ合って結論が出ないとき
- 社会問題についてSNSでさまざまな人が意見を交わしているとき
「甲論乙駁」を使う時は、以下の点に注意しましょう。
- ケンカのような単なる言い争いには使わず、きちんと意見を出し合う場面で使う。
- その場が白熱しても、解決や結論がなかなか出ない状況を表すときに使う。
- 人を悪く言うためではなく、中立的に「意見がぶつかり合っている」ことを表す言葉。
甲論乙駁の例文①
クラスで文化祭の出し物を決めるために話し合っている場面です。
 ヒロト
ヒロト文化祭の出し物、演劇にするか屋台にするか、全然決まらないんだよ。
 コトハ
コトハそれはみんなの意見が甲論乙駁になって、まとまらないのね。
 ヒカル
ヒカルええ、こういうときに『甲論乙駁』って使うと、意見が入り乱れて収拾がつかない様子を的確に表せるわよ。
この例文では、学校行事の話し合いで意見が分かれて結論が出ない様子を表現しています。
甲論乙駁の例文②
家族で夕食のメニューを決める場面です。
 ヒロト
ヒロト今日の晩ごはん、カレーかハンバーグかで、家族が大もめなんだ。
 コトハ
コトハあら、それは甲論乙駁ね。みんなが好きなものを言って、なかなか決まらないんでしょ。
 ヒカル
ヒカルそうそう。食事のメニューみたいな小さなことでも、意見がぶつかってまとまらないときに『甲論乙駁』はぴったりの言葉なのよ。
この例文では、家族の意見がバラバラでなかなか夕食が決まらない様子を「甲論乙駁」と表しています。
甲論乙駁の例文③
友達どうしで「どこで遊ぶか」を決めようとしている場面です。
 ヒロト
ヒロト今度の休み、ボウリングに行くかカラオケに行くかで、みんな意見がバラバラだよ。
 コトハ
コトハそれってまさに甲論乙駁ね。誰も譲らないから、決まらないのね。
 ヒカル
ヒカル友達同士の話し合いでも、こうして意見が入り乱れることはよくあるの。そんな場面を一言で表せるのが『甲論乙駁』なのよ。
この例文では、遊びの予定を決めるときに意見が対立して決まらない様子を表現しています。
「甲論乙駁」の言い換え表現を例文を使ってわかりやすく解説
「甲論乙駁」には以下のような言い換え表現があります。
【甲論乙駁の言い換え表現】
①意見が対立する:日常的にもっとも使いやすい表現です。「甲論乙駁」が少し堅い印象なのに対し、「意見が対立する」は、会話や文章で誰にでも伝わりやすいシンプルな言い方です。
②話がまとまらない:「甲論乙駁」が「反論し合う」ニュアンスを持っているのに対し、「話がまとまらない」はもう少し柔らかく、結果として結論が出ないことに焦点をあてています。
「意見が対立する」の例文
クラスで文化祭の出し物を決める話し合いです。
 ヒロト
ヒロト文化祭で劇をやるか模擬店をやるかで、全然決まらないんだよ。
 コトハ
コトハそれは意見が対立しているのね。どっちもやりたい人がいて、譲らないんでしょ?
 ヒカル
ヒカル『甲論乙駁』だと少し難しいけど、『意見が対立する』なら日常会話で自然に使えるの。どちらの考えも正しい可能性があるけれど、ぶつかってまとまらない状態を表しているのよ。
「甲論乙駁」はやや文学的・堅い言葉で、議論が激しくぶつかる印象があります。
「意見が対立する」はもっと一般的で、学生や家庭の話し合いでも使いやすい表現です。
「話がまとまらない」の例文
友達同士で旅行先を決める話し合いです。
 ヒロト
ヒロト旅行の行き先を決めようとしてるんだけど、海派と山派で決まらないんだよな。
 コトハ
コトハあら、それは話がまとまらない状態ね。
 ヒカル
ヒカル『甲論乙駁』はお互いに反論しているイメージが強いけど、『話がまとまらない』はもっと柔らかい表現なの。日常会話ではこの言い換えが一番自然で伝わりやすいのよ。
「甲論乙駁」は真剣な討論や堅い文章に使われやすい言葉です。
一方、「話がまとまらない」は日常的な会話にぴったりで、反論の激しさよりも「結論に至らないこと」に焦点を当てた表現です。
「甲論乙駁」の類義語
「甲論乙駁」には、以下のような似た意味をもつ言葉があります。
【甲論乙駁の類義語】
weblio類語辞典より引用
- 賛否両論(さんぴりょうろん):賛成と反対の両方の意見。意見が反対の者同士が向かい合っていて、結論が出ない状況をいう。
- 諸説紛紛(しょせつふんぷん):様々な意見が出て議論がまとまらないこと
「賛否両論」の例文
「賛否両論」とは、ある物事に対して賛成の意見と反対の意見があり、評価が分かれることを意味します。多くの人の意見が正反対に分かれるときに使います。
 ヒロト
ヒロトあの新しい映画、すごく話題になってるけどどうなんだろ?
 コトハ
コトハ『賛否両論』みたいよ。面白いって人もいれば、つまらないって人もいるの。
 ヒカル
ヒカルそうね。『甲論乙駁』は議論が続いて収拾がつかない様子を表すけど、『賛否両論』は意見が賛成と反対にハッキリ分かれていることを表すのよ。
この例文では、新しい映画の評価が真っ二つに分かれていることを表しています。議論が続いているというより、「意見の評価が割れている」というニュアンスが強いのが「賛否両論」です。
「諸説紛紛」の例文
「諸説紛紛(しょせつふんぷん)」とは、いろいろな意見や説が出ていて、どれが正しいのか定まらないことを意味します。学問的な議論や歴史の解釈などに使われやすい言葉です。
 ヒロト
ヒロト卑弥呼の墓って、どこにあるのか結局わかってないんだよね?
 コトハ
コトハそうなのよ。『諸説紛紛』で、あちこち説が出ているの。
 ヒカル
ヒカルここで『甲論乙駁』と言うと、意見がぶつかり合っている印象になるわ。でも『諸説紛紛』は、ただ多くの説があって結論が出ていない、というニュアンスなの。
この例文では、歴史上の出来事についてさまざまな説が出ている様子を表しています。日常会話でも使えますが、学問や研究など少し堅めの場面で特によく使われる表現です。
「甲論乙駁」の対義語
「甲論乙駁(こうろんおつばく)」には、はっきりとした対義語はありません。ですが、あえて反対の意味を持つ言葉を選ぶと、「満場一致(まんじょういっち)」 と 「衆口一致(しゅうこういっち)」 が挙げられます。どちらも「みんなの意見がそろう」という意味で、意見がぶつかってまとまらない「甲論乙駁」とは逆のイメージです。
【甲論乙駁の対義語】
スッキリより引用
- 満場一致(まんじょういっち):その場所にいる全員の意見が一つになること。だれも異議がないこと。
- 衆口一致(しゅうこういっち):多くの人の意見や評判がぴったり合うこと。▽「衆口」は多くの人の口から出る言葉。「一致」は一つになる意。
「満場一致」の例文
「満場一致」とは、その場にいる全員の意見が一致することを表します。会議や話し合いで、誰も反対せずに賛成する場面でよく使われます。
 ヒロト
ヒロトクラスで文化祭の出し物を決めたけど、すぐに決まったよ。
 コトハ
コトハあら、珍しいわね。みんな『満場一致』で同じ意見だったの?
 ヒカル
ヒカルそういうときに『満場一致』を使うのよ。全員が同じ意見を持っていて、異論が出ないからすぐに結論が出たことを表すの。
この例文では、クラスの話し合いで全員が同じ意見を出したために、迷うことなく決まった様子を表しています。議論が白熱して収拾がつかない「甲論乙駁」とは正反対の状況です。
「衆口一致」の例文
「衆口一致」とは、多くの人の意見が一致することを意味します。「満場一致」が「全員一致」であるのに対し、「衆口一致」は「大多数が同じ意見」というニュアンスがあります。
 ヒロト
ヒロト新しい部長の提案、どうだった?
 コトハ
コトハほとんどの人が賛成して、『衆口一致』だったわね。
 ヒカル
ヒカル『衆口一致』は、みんなが同じ意見を持つことを表すけど、『満場一致』と違って必ずしも全員ではないの。大多数の意見がそろったときに使うのよ。
この例文では、会社の会議でほとんどの人が賛成した様子を表しています。全員でなくても、大多数の意見が一致すれば「衆口一致」と言えます。
このように、「甲論乙駁」が意見のぶつかり合いを表すのに対し、「満場一致」「衆口一致」は意見がそろってスムーズにまとまる場面を表します。状況に応じて使い分けると、表現がより的確になります。
「甲論乙駁」の英語表現
「甲論乙駁」をそのまま英語に置き換えることは難しいですが、意味に近い英語表現はいくつかあります。ここでは特によく使えるものとして、以下の2つの表現を紹介します。どちらも「甲論乙駁」が持つ「意見がぶつかってまとまらない」というニュアンスを表すことができます。
【甲論乙駁の英語】
- “conflicting opinions”:意見が対立する
- “heated debate”:白熱した議論
「conflicting opinions」の例文
“conflicting opinions” は「対立する意見」という意味です。お互いの考えが食い違って、簡単にはまとまらない状況を表します。
 ヒロト
ヒロト「甲論乙駁」を英語で表現した例文を教えて!
 コトハ
コトハ"There were conflicting opinions about the new school rules, and no agreement was reached."のように表現することができます。
日本語訳:新しい校則について意見が対立し、結論は出なかった。
 ヒカル
ヒカルこの表現は、学校や職場など日常的な場面でも使いやすいシンプルな言い方です。「甲論乙駁」と同じように、意見がぶつかり合ってまとまらない状態をわかりやすく伝えられます。
「heated debate」の例文
“heated debate” は「白熱した議論」という意味です。お互いが強く意見を主張し合い、なかなかまとまらない様子を表します。
 ヒロト
ヒロト「甲論乙駁」を英語で表現した例文をもう1つ教えて!
 コトハ
コトハ"The meeting turned into a heated debate about the budget plan."
のように表現することができます。
日本語訳:会議は予算案をめぐって白熱した議論になった。
 ヒカル
ヒカルこの表現は、議論が活発すぎて収拾がつかないような雰囲気を伝えるのにぴったりです。「甲論乙駁」が持つ「意見が入り乱れている」イメージに近いニュアンスを英語で表せます。
まとめると、日常会話では「conflicting opinions(意見が対立する)」がわかりやすく、ニュースや議論の場面では「heated debate(白熱した議論)」が自然に使える表現です。
まとめ
甲論乙駁(こうろんおつばく)とは、意見がぶつかり合い、なかなかまとまらない状態を表す四字熟語です。学校の話し合い、家族や友人との相談、社会問題の議論など、日常から専門的な場面まで幅広く使うことができます。
また、似た意味の言葉として「賛否両論」や「諸説紛紛」があり、反対の意味に近い表現として「満場一致」や「衆口一致」があります。さらに英語では “conflicting opinions” や “heated debate” などで表現でき、状況に応じて言い換えられるのもポイントです。
「甲論乙駁」という言葉を知っていると、単に「意見がまとまらない」と言うよりも、議論の激しさや収拾のつかない様子を的確に伝えることができます。日常生活や学習の中でぜひ使ってみてください。
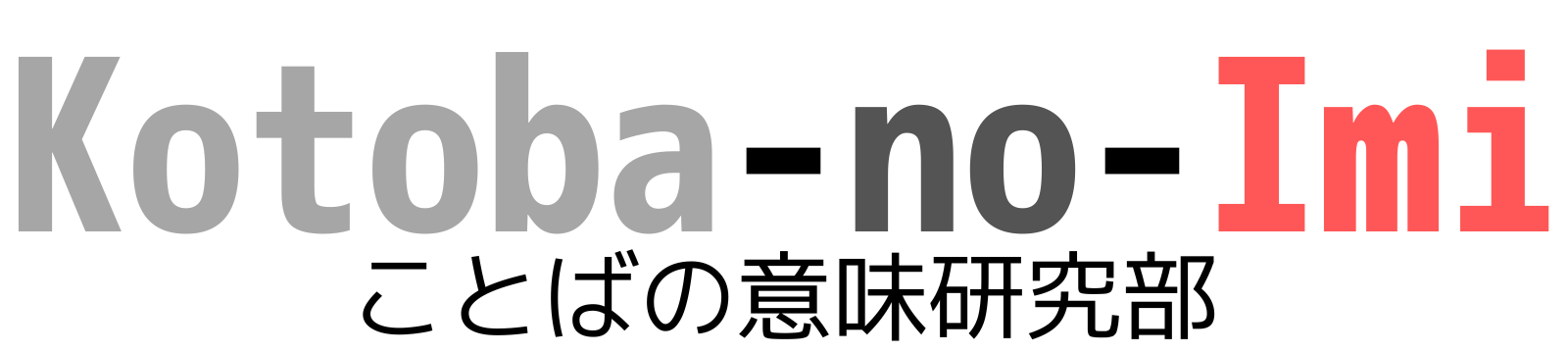
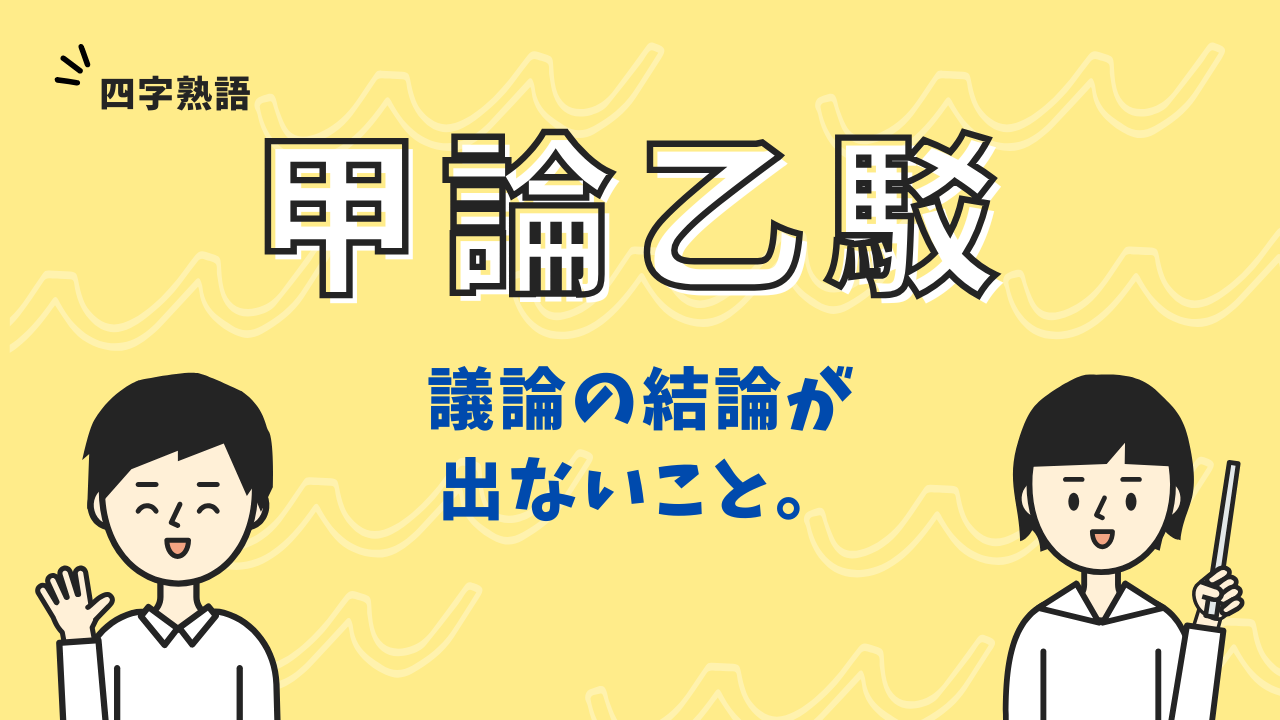
コメント