国際経済や世界史を学んでいると、必ず目にするのが「GATT(ガット)」という言葉です。新聞やニュース記事でもたびたび登場し、大学入試や資格試験では頻出のキーワードでもあります。
「GATTってWTOの前身って聞いたことあるけど、実際どういうものなの?」
「日本とGATTにはどんな関係があったの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
GATTは1947年に誕生し、第二次世界大戦後の混乱を収め、国際社会に「自由貿易」というルールを根づかせるための重要な枠組みでした。現在はWTO(世界貿易機関)へと発展的に移行しましたが、その理念とルールは今も国際貿易の基盤として生き続けています。
この記事では、GATTの意味・歴史・役割・WTOとの違い・日本との関わり・受験での覚え方や実際の出題例まで、幅広く解説していきます。
「GATT」という言葉が、国際経済の中でどんな意味を持っていたのかを、ぜひ一緒に学んでいきましょう。
GATTとは?意味と基本概要
まずはGATTの基本から押さえておきましょう。
GATTは、 General Agreement on Tariffs and Trade の略で、日本語では「関税及び貿易に関する一般協定」と呼ばれます。
1947年に23か国が署名し、翌年1948年に発効しました。戦後の世界は保護主義的な政策が強まりがちで、各国が関税を高くして貿易を制限すると、経済の停滞や国際的な対立が再び生まれる恐れがありました。そこで、国際社会が協力して「自由で公平な貿易」を守るために作られたのがGATTです。
この協定は「国際機関」ではなく、あくまで「国際的な取り決め」であった点が特徴です。しかし実質的には、戦後の自由貿易を支える基盤として機能し、後に誕生するWTOの前身となりました。
・正式名称は「関税及び貿易に関する一般協定」
・1947年に成立、1948年発効
・WTOの前身として自由貿易のルール作りを担った
「GATTの意味」
 ヒロト
ヒロトねえコトハ、GATTってそもそも何のことなの?
 コトハ
コトハ簡単に言うと、戦後にできた国際貿易のルールよ。正式には『関税及び貿易に関する一般協定』って言って、各国が勝手に関税を上げたりして世界経済が混乱しないように作られたの。
 ヒロト
ヒロトなるほど、戦争の後だからこそ必要だったんだね。
 ヒカル
ヒカル補足すると、最初に23か国が署名して始まったの。これは国際機関じゃなくて協定だけど、実際には世界の貿易を守る仕組みとして働いたのよ。だからこそ、今もWTOのルールの一部として残っているの
GATT成立の歴史と背景
戦後の国際社会とGATT誕生の背景
第二次世界大戦の反省から、各国は「保護主義的な経済政策が戦争を招いた」という教訓を得ました。第一次世界大戦後の1929年世界恐慌では、アメリカがスムート・ホーリー法で高関税を導入したことを皮切りに、各国が貿易を閉ざし、経済の悪化が国際緊張を高めていきました。その失敗を繰り返さないために、「戦後は自由で開かれた貿易体制をつくろう」という考え方が強まりました。
1944年のブレトンウッズ会議では、国際通貨基金(IMF)や世界銀行が設立されましたが、貿易に関しても「国際貿易機関(ITO)」をつくる構想が持ち上がりました。しかし、アメリカ議会の反対などによりITOは実現せず、その代わりとして暫定的に機能することになったのがGATTです。
GATTの交渉ラウンド
GATTは単なる取り決めで終わらず、各国が集まって関税や貿易ルールを見直す「ラウンド交渉」を重ねました。これにより、世界的な関税水準は次第に引き下げられ、自由貿易の土台が固まっていきました。
代表的なラウンドを整理すると次のようになります。
GATTの主要ラウンド
| ラウンド名 | 年代 | 主な内容 |
|---|---|---|
| ジュネーブ | 1947年 | 初回交渉、関税引き下げ |
| ケネディ・ラウンド | 1964-67年 | 工業製品の関税削減 |
| 東京ラウンド | 1973-79年 | 非関税障壁への対応 |
| ウルグアイ・ラウンド | 1986-94年 | 農業・サービス、知的財産、WTO設立 |
この中でも特に重要なのが ウルグアイ・ラウンド で、ここでの合意をもとに1995年にWTOが設立されました。つまり、GATTの歴史はそのままWTOの誕生に直結しているのです。
「GATTの歴史」
 ヒロト
ヒロトどうしてわざわざGATTをつくったの? IMFとか世界銀行もあったんでしょ?
 コトハ
コトハそうね。でもIMFや世界銀行はお金の流れや開発支援を扱う組織だったの。貿易そのものを自由にする仕組みが必要だったのよ。
 ヒロト
ヒロトへえ、じゃあ最初は別の国際機関をつくる予定だったんだね?
 コトハ
コトハそうなの。本当は『国際貿易機関(ITO)』を作ろうとしたけど、アメリカ議会が批准を拒否したから実現しなかったの。その代わりに暫定措置としてGATTが動き始めたの。
 ヒカル
ヒカル補足するとね、GATTはただの協定にとどまらず、『ラウンド交渉』という国際会議を繰り返したの。たとえば東京ラウンドでは非関税障壁、ウルグアイ・ラウンドでは農業やサービスまで議論が広がったの。こうしてWTOにつながっていったのです。

GATTの役割と基本原則
GATTの役割
GATTの最大の役割は、戦後の国際社会で「自由貿易を守るための共通ルール」をつくることでした。各国が独自に高い関税や輸入制限をかけると、貿易が停滞し、国際関係の不安定さが増してしまいます。そこで、加盟国が協力して「関税を下げる」「貿易を透明にする」「差別しない」という基本原則を共有し、国際経済の安定を支えました。
実際に、GATT体制のもとで各国の平均関税率は大幅に引き下げられ、世界貿易は戦前と比べて飛躍的に拡大しました。これは、日本のように輸出主導で成長した国にとっても大きな追い風となりました。
GATTの基本原則
GATTを理解するうえで欠かせないのが「基本原則」です。代表的なものは以下の3つです。
・最恵国待遇(Most-Favoured-Nation, MFN)
ある国に特別な貿易上の利益を与えたら、他のすべての加盟国にも同じ待遇を与えなければならない。差別を防ぐ仕組み。
・最恵国待遇(Most-Favoured-Nation, MFN)
ある国に特別な貿易上の利益を与えたら、他のすべての加盟国にも同じ待遇を与えなければならない。差別を防ぐ仕組み。
・貿易の透明性
貿易制限は関税を基本とし、数量制限や輸入禁止のような不透明な措置は避ける。これにより、貿易ルールが分かりやすくなる。
これらの原則は、今でも国際貿易の基本ルールとして機能しています。
「GATTの基本原則」
 ヒロト
ヒロトねえ、GATTって実際にはどんなルールを決めてたの?
 コトハ
コトハ代表的なのは『最恵国待遇』よ。ある国に安い関税を適用したら、ほかの加盟国にも同じ条件を与えなきゃいけないの。
 ヒロト
ヒロトえ、じゃあ特別な仲良し国だけを優遇することはできないんだ?
 コトハ
コトハその通り!それをやると不公平になるからね。それに『内国民待遇』も大事よ。輸入品だからといって差別的に扱っちゃダメなの。
 ヒカル
ヒカル補足すると、『透明性』も忘れちゃいけないわ。数量制限や輸入禁止みたいな不透明な規制はなるべく避けて、関税という分かりやすい形で調整するの。こうすることで、貿易がルールに基づいて公平に進むようになるんのです。

GATTとWTOの違い
GATTとWTOの位置づけ
GATTは「協定(agreement)」であり、正式な国際機関ではありませんでした。事務局はあったものの、法的拘束力や紛争解決の力は弱く、「加盟国同士の合意」で成り立つ性質が強かったのです。
一方、1995年に発足したWTO(世界貿易機関, World Trade Organization)は、はっきりとした国際機関として機能します。加盟国は2025年現在で160以上。農業、サービス、知的財産権など、従来のGATTでは対象外だった分野にもルールを広げています。さらに、WTOは強力な紛争解決制度を持ち、加盟国間のトラブルを公平に解決する仕組みを備えています。
つまり、GATTは自由貿易の「基礎工事」を担い、WTOはその上に立つ「本格的な建物」のような存在だといえるでしょう。
GATTとWTOの違いを整理
比較表:GATTとWTOの違い
| 項目 | GATT(1947〜1994) | WTO(1995〜現在) |
|---|---|---|
| 性格 | 協定(条約) | 国際機関 |
| 対象 | 主に関税・物品貿易 | 農業・サービス・知的財産も対象 |
| 加盟国数 | 23か国から始まった | 160か国以上(ほぼ全世界) |
| 紛争解決 | 勧告的、強制力に乏しい | 強制力ある紛争解決機関を設置 |
| 存続 | WTOの一部として「GATT1994」として残存 | WTO協定全体に組み込まれて活動 |
 ヒロト
ヒロトGATTとWTOってよくセットで出てくるけど、どんな違いがあるの?
 コトハ
コトハ一番の違いは性格ね。GATTはあくまで『協定』で、国際機関ではなかったの。だから実際の力は弱かったのよ。
 ヒロト
ヒロトなるほど。じゃあWTOはちゃんとした組織なんだ?
 コトハ
コトハそう。1995年にできたWTOは正式な国際機関で、貿易全般を扱うの。農業、サービス、知的財産権までカバーしているわ。
 ヒカル
ヒカル補足すると、紛争解決の力も全然違うの。GATTのときは加盟国が従わなくても強制できなかったけど、WTOは仲裁機関があって加盟国は従わなきゃいけないの。だから現代の国際貿易はWTOのルールで守られているんだよ。
現在の活動内容と意義
GATTは今も生きている?
「GATTはもう終わった協定」と思われがちですが、実はそうではありません。1995年にWTOが発足した際、GATTは廃止されたのではなく、「GATT 1994」としてWTO協定の一部に組み込まれました。つまり、GATTの基本的なルールは今も現役で、WTOの枠組みの中で生き続けているのです。
現在の意義
現代の貿易は、工業製品だけでなく農産物やサービス、知的財産など複雑な要素を含んでいます。そのため、WTOは幅広い役割を果たしていますが、その基盤はあくまでGATTで築かれた「関税を中心に据えた自由貿易のルール」です。
例えば、今でも加盟国は「最恵国待遇」「内国民待遇」「透明性の確保」といったGATT時代の原則を守る義務があります。これがあるからこそ、世界貿易が予測可能で安定した形で進められているのです。
現代における意義のまとめ
- GATTの基本原則は今も国際貿易ルールの根幹
- WTOに発展的に吸収されながら「GATT 1994」として存続
- 世界経済の安定と予測可能性に寄与
「GATTの現在の意義」
 ヒロト
ヒロトGATTってもう過去のものかと思ってたけど、今も残ってるの?
 コトハ
コトハ完全に消えたわけじゃないの。1995年にWTOに移行したとき、『GATT 1994』って名前で協定の一部として残ったのよ。
 ヒロト
ヒロトへえ、じゃあ今の世界貿易にもGATTの考え方が生きてるんだね。
 ヒカル
ヒカルその通り。たとえば『最恵国待遇』や『内国民待遇』といった原則は今も有効で、加盟国はそれを守らなきゃいけないの。だからGATTは“現代の国際貿易ルールの土台なのです。
日本とGATTの関わり
日本の加盟と背景
日本がGATTに加盟したのは1955年(昭和30年)のことです。第二次世界大戦後、日本は国際社会から孤立し、経済的にも厳しい状況にありました。しかし、国際的な経済秩序に復帰することは、日本の再建と発展のために欠かせないものでした。
当初、日本の加盟に対しては欧米諸国の警戒感もありました。敗戦国であり、輸出競争力を急速に高めつつあった日本に対し、「安売り輸出で市場を荒らすのではないか」という懸念があったのです。それでも加盟が認められたのは、日本が戦後復興を進めるなかで国際経済への参加を強く求めたこと、そして冷戦下で日本を自由貿易体制に取り込むことがアメリカにとっても有利だったことが背景にありました。
日本経済への影響
加盟後、日本はGATTの自由貿易ルールのもとで貿易拡大を進めました。自動車や家電といった工業製品の輸出が増加し、「輸出立国」としての地位を確立していきます。これが高度経済成長の大きな原動力となりました。
また、GATT加盟は国際社会への復帰という象徴的な意味も持っていました。敗戦後、占領期を経て再び国際舞台に戻るうえで、経済分野での信頼を取り戻す大きな一歩となったのです。
・日本は1955年にGATT加盟
・加盟は高度経済成長の基盤となった
・国際社会への復帰という政治的意味合いも大きかった
「日本とGATT」
 ヒロト
ヒロト日本はいつGATTに入ったの?
 コトハ
コトハ1955年よ。戦後の復興期に加盟して、国際経済に復帰したの。
 ヒロト
ヒロトでも当時、日本はまだ経済的に弱かったんじゃないの?
 コトハ
コトハそうね。ただ日本は輸出をどんどん伸ばしていたから、欧米からは『安売り輸出で脅威になるんじゃないか』と警戒されていたのよ。
 ヒカル
ヒカル補足するとね、日本の加盟は単に経済的な意味だけじゃなく、政治的にも大きかったの。自由貿易体制に参加することで国際社会に受け入れられ、高度経済成長の基盤を築くことができたのです。
GATTと受験対策
入試での頻出テーマ
GATTは世界史・日本史・政治経済など、さまざまな科目で問われる頻出キーワードです。特に出やすいのは以下のポイントです。
- 成立年:1947年に署名、1948年発効
- 性格:協定(条約)であって国際機関ではない
- 基本原則:最恵国待遇・内国民待遇・透明性
- ラウンド交渉:特に「ウルグアイ・ラウンド」からWTO設立へ
- 日本の加盟:1955年、日本経済の国際復帰と高度成長につながる
これらは「GATTとWTOの違い」とセットで出題されることが多いため、丸暗記ではなく関連づけて理解しておくと効果的です。
実際に出題された問題例
例題1(世界史)
1995年に発足したWTOの前身となった協定を答えよ。
→ 正解:GATT(関税及び貿易に関する一般協定)
例題2(政治経済)
次の交渉ラウンドと内容の組み合わせのうち、正しいものを選べ。
A. 東京ラウンド ― 農業とサービス貿易
B. ウルグアイ・ラウンド ― WTO設立に合意
→ 正解:B
例題3(日本史)
日本が国際経済に復帰したきっかけとなった1955年の出来事として正しいものを答えよ。
→ 正解:GATT加盟
ポイントは「用語単体」ではなく「年号」「出来事」「交渉ラウンド」との関連で出題されることです。
覚え方のコツ
- 「1947年GATT → 1995年WTO」と年号の流れをつかむ
- 「GATT=協定、WTO=国際機関」と対比で整理
- 「日本は1955年加盟」で高度経済成長とリンクさせて記憶
「受験対策としてのGATT」
 ヒロト
ヒロトGATTって受験ではどんなふうに出るの?
 コトハ
コトハたとえば『WTOの前身は?』っていう問題が典型的ね。それにラウンド交渉や日本の加盟年もよく問われるわ。
 ヒロト
ヒロトラウンド交渉ってどれが重要なの?
 コトハ
コトハ特に『ウルグアイ・ラウンド』よ。ここで農業やサービスまで議論して、最終的にWTOが誕生したの。
 ヒカル
ヒカル補足するとね、年号を押さえるのも大事。『1947年GATT設立』『1955年日本加盟』『1995年WTO発足』。この流れで覚えておくと、どんな試験でも得点しやすいわよ。

まとめ
GATTの全体像を振り返る
ここまで見てきたように、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)は、戦後の国際経済を立て直すために生まれた協定でした。1947年に署名され、1948年に発効。その後は「ラウンド交渉」を通じて貿易の自由化を進め、1995年にWTOへと発展的に移行しました。
GATTの基本原則――「最恵国待遇」「内国民待遇」「透明性」――は、今日のWTO協定にも受け継がれており、今なお世界の貿易を支えるルールとして機能しています。
日本にとってもGATT加盟は大きな転機でした。1955年の加盟によって国際社会に復帰し、高度経済成長への道を開くことができました。経済的にも政治的にも、その意義は非常に大きかったのです。
受験勉強では「1947年設立」「1955年日本加盟」「1995年WTO発足」という年号の流れ、そして「協定としてのGATT」と「国際機関としてのWTO」という対比を押さえておくことが得点のポイントになります。
 ヒロト
ヒロトGATTって最初はただの協定だったけど、世界の自由貿易を支える大事なルールだったんだね。
 コトハ
コトハそう。戦後の混乱から立ち直るために作られて、その後のWTOへとつながっていったの。まさに“自由貿易の土台”ね。
 ヒロト
ヒロト日本にとっても1955年の加盟は大きな意味があったんだ。
 コトハ
コトハええ。経済成長の後押しになったし、国際社会に受け入れられるきっかけにもなったのよ。
 ヒカル
ヒカル試験対策としては、GATTとWTOの違いを整理して、年号をしっかり覚えておくといいわ。これで“GATTって何?”と聞かれても自信を持って答えられるはずよ。
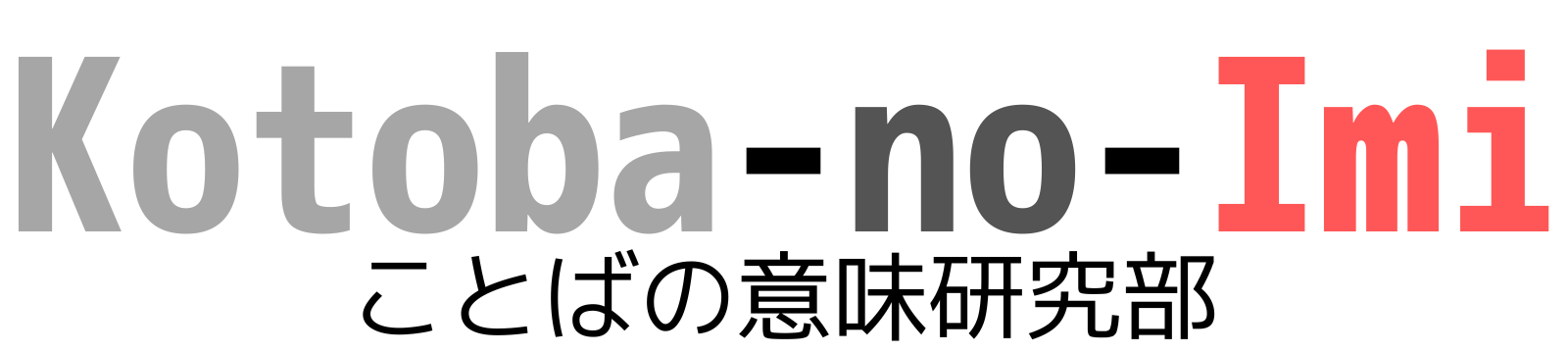

コメント